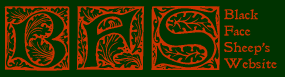
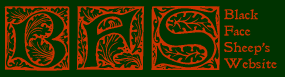
THE LORD GOD MADE THEM ALL (1981, Michael Joseph Ltd.)
ヘリオット先生の7冊目の作品集です。
タイトルはセシル・フランシス・アレグザンダーの聖歌の最後の一節、「神がすべてをつくりたもうた」です。献辞はアルフ・ワイトの孫、ゾーイ(息子夫婦のジミーとジルの子)に捧げられています。
この作品集を出すまでには4年の年月が必要でした。
その理由の一つは、写真集"JAMES HERRIOT'S YORKSHIRE"の執筆に時間をとられたことですが、もう一つの理由は「大きな本が好き」なアメリカのマーケットに対応するためにたくさんのエピソードを書かなければならなかったからでした。
そんなわけで、この作品集は以前の作品集と異なり、英国でもアメリカでも同時に発刊されました。
前述のグレアム・ロードによるアルフ・ワイトの伝記、"THE LIFE OF A COUNTRY VET"によれば、この作品集は「アルフ・ワイトの才能の枯渇を予感させる内容」と、こきおろされています。
しかし、私はこのロード氏の意見には賛成できません。
確かに、他の作品集と異なり、様々な時代のエピソードが混在していてまとまりがないし、ヨークシャーを離れて1960年代初期にソ連やトルコに旅行したときの日記なども紹介されていたりして、ヘリオット・サーガの中では異色の作品集です。
でも、アルフが成長しつつある息子や娘とともに一番楽しい時代を過ごした1950年代のエピソードは、その構成の乱雑さを補って余りあるものがあると思います。
また、アルフの息子ジミーが書いているように、この本は「獣医の喜びだけでなく、どの獣医も避けて通ることのできない悲しみ」についても描出されており、よりいっそうの深みを感じます。
最後まで日本語完訳が完成しなかった作品でしたが、2004年の4月初旬、待望の完訳版が登場しました。タイトルは「毎日が奇跡:(集英社文庫、大熊栄訳)」で、すべてのチャプターがもれなく翻訳されています。
下記にTHE LORD GOD MADE THEM ALLの各章の概要をご紹介します。
章 内容 邦訳 1 リプリー老人の農場にやってくると、本当に「帰ってきた」という実感がした。この農場に至るまでの7つの門にはいつも苦労した。特に7番目の門は体に危険をおよぼすほどおんぼろで悪質な門だった。また、牛の去勢を依頼するタイミングもいつも遅くて、巨大な牛をおびえながら去勢していた。リプリー老人に門の修理、そして牛が幼い時に往診させてくれと頼むと「ああ、わかっただ、うけあうだよ」と調子は良いのだが、いつも言葉ばかり。戦争から帰っても、この状況になんら変化はなかった。凶暴な7番目の門はさらに悪意に満ちたものになっており、服を切り裂かれてしまう。また、子牛の去勢を頼まれるも、これもやはり巨大な牛に育ってしまっていたのだった。リプリー老人に、再度改善を要求するのだが、答えはいつものように「二度としない、うけあうだよ」、であり、あてにならないことおびただしいものがあった。 毎日が奇跡:第1章 (集英社文庫、大熊栄訳) 2 夜中に電話。泣きながら往診して欲しいと言う。ハンフリー・コッブ氏を訪問すると、彼のビーグル、マートルがあえいでいた。ストーブの近くにバスケットを置いたからで、まったく健康だった。しかしハンフリーがどうしてもというので、ビタミン剤を与える。彼は競馬に行き、マートルをほったらかしにしたので罪の意識で泣いていた。その後、ハンフリーは競馬に出かけるたびに、夜中に電話をよこし、そのたびに往診するが、マートルはなんでもなかった。ヘリオットはマートルを治しているのではなく、コッブさんを治しているのだった。ある晩電話をもらったとき、さすがに往診を断る。しかし産褥子疳であることに気づき、慌てて往診し、カルシウム注射で命を取り留める。しかし、ハンフリーは「今日は本当はなんでもなかったんだよね」と言うのだった。 動物物語:第8章 (集英社文庫、大熊栄訳)
毎日が奇跡:第2章 (集英社文庫、大熊栄訳)
3 ヨークシャーの農業社会は変化を迎えていた。サルファ剤が登場しより科学的になったし、小さな農家はどんどん消えていくし、シーグフリードは結婚して診療所を出て行った。あるとき、シーグフリードの自動車が故障したので、スペアとして中古車をもう一台買うことになった。シーグフリードはヘリオットとカーディーラーを乗せて試乗に出かけるが、シーグフリードの運転は超過激で、一同肝を冷やす。ブレーキの効きが悪いのでもう一台試乗したいという。ディーラーはもう一台あることはあるが、自分で持ってくると言わない。明らかに同乗を拒んでおり、後で他のものに持ってこさせると言うのだった。シーグフリードのエキセントリックな性格とデイルズの風景は不変だった。 毎日が奇跡:第3章 (集英社文庫、大熊栄訳) 4 診療所の元アシスタントだったジョン・クルックスは、ヨークシャーの南部の古都ビバリーで開業しており、ときどき近くのハル港からソ連に出航するう家畜運搬船の獣医をつとめることがあった。彼はその仕事をヘリオットに回してくれた。1961年10月28日にハル港から300トンのデンマーク船、アイリス・クラウゼン号に乗船し、ソ連のクライペダに向かう。383匹のロムニーマーシュ種とリンカーン種、価格にして合計2万ポンドを運ぶのだ。家畜船だが、羊を乗せるのは初めてだった。夜9時に出港し、船は揺れ始めた。 毎日が奇跡:第4章 (集英社文庫、大熊栄訳) 5 長男のジミーは、4歳のときから往診についてくるようになった。往診の道中、彼とクイズをするのは大きな楽しみだった。ジミーは農夫が履いているような本格的なブーツを欲しがる。そんな小さな子供用のブーツは見つからないだろうと思っていたが、へレンは小さなサイズのブーツを探してきたのだった。ジミーのように考える子供は他にもいたのだ。ジミーはよい子だが、いたずら小僧だった。あるとき、手術をしていると、ジミーが壁のフジの木を登っているのが見えた。心配してみていると、彼は、案の定、そこから落ちてしまった。幸い怪我はなかったが、「こんなことをすると往診には他の子を連れて行くぞ」と叱ると、彼は「僕のブーツ、その子にあげちゃうの?」と心配げに聞くのだった。 毎日が奇跡:第5章 (集英社文庫、大熊栄訳) 6 農場に不気味な東洋人が現れ、農夫の妻は「ドクター・フーマンチュー!」と恐慌に陥る。彼はモンゴル系ロシア人の捕虜だった。戦時中、各国の戦時捕虜が農場を手伝いに来ていた。ある日、プレストン農場の牛が脱臼した。治療のために、近くにいたドイツ人の捕虜に頼むと、喜んで手伝ってくれた。彼らが故郷に帰ったとき、良い土産話になるだろう。またハリソンの農場の牛に巨大な腫瘍ができた。手術しようとするが麻酔も打てないぐらいに凶暴。ルイジというイタリア人捕虜が、「耳をしぼりあげる」ことで動きを封じ、大いに驚く。谷にはロシア人捕虜の合唱が響いていた。 毎日が奇跡:第6章 (集英社文庫、大熊栄訳) 7 船内日記10月29日。朝食はデンマーク風で豪華。船員たちと片言の英語で会話。朝食後、羊たちの診察を行う。びっこを引いていた羊にテラマイシンのスプレー。目を患っている羊にクロラムフェニコール軟膏を塗る。昼食はさらに豪華。ホテル・リッツ並の素晴らしい料理が並ぶ。コックのニールセンを褒めると、おおいに喜ぶ。羊たちを見に行くとリンカーン種の一匹が咳をしているのが気になる。夕食も当然豪華。食後、船員たちとシュナップスとビールを飲み、語り合う。船乗りの話は面白かった。 毎日が奇跡:第7章 (集英社文庫、大熊栄訳) 8 文学好きの実習学生ノーマン・ボーモントによれば、牛の帝王切開はいまや当たり前の手術で、犬の避妊と同じぐらい簡単だという。昨今は学生に教わることが多い。ブッシェルさんの牛の助産に行く。その牛、ベラは小さな牛。中を探ってみると、巨大な子牛。帝王切開しかない。ノーマンに手伝わせるが、実は彼はほとんど帝王切開の経験がないことがわかる。ヘリオットはノーマンを呪いながら手術を続けるが、無茶苦茶になってしまう。子宮と間違えて瘤胃を切り、汚物が飛び散り、惨憺たる有様になる。途中で麻酔が覚め始て牛は立ち上がろうとする。もう腹膜炎は必至、というひどい結果になったが、奇跡的に手術は成功した。 毎日が奇跡:第8章 (集英社文庫、大熊栄訳) 9 船内日記10月30日。船はキール運河に到着。ドイツ領なのでパスポートをチェックされる。ここで初めて乗船者名簿にヘリオットの名前が載ることになるが、称号はなんと上級船員。6時間かけて運河を通過し、バルト海へ。羊の世話をする若者、ラウムと仲良くなる。彼は羊を大きなテディベアを抱くように扱う。毎晩10時に最終診察をすることにする。調子の悪い羊たちも、それほどひどくなっていなくて安心する。夜、ラウムたちと飲む。彼らは快活で礼儀正しい船員だった。 毎日が奇跡:第9章 (集英社文庫、大熊栄訳) 10 「家畜の足が臭くなる病気」の新薬を手に入れた。首に注射を打つだけでよいとの事。半信半疑で使ってみると、まさしく薬屋の言うとおりだった。マクスウェルさんの農場でこの病気の牛が出たので、このM&B693を注射する。確かに足は治ったが、首の静脈炎を引き起こし、死亡させてしまう。マクスウェルさんは寛大に許してくれた。次に彼の牛が腎炎を起こし、サルファ剤を使うが、全快しない。なんとしてもマクスウェルさんの恩義に報いたいので、初めての薬、ペニシリンという抗生物質を使う。なにしろ乳腺炎の牛用の軟膏状のペニシリンを無理やり注射したので、用法も分量も無茶苦茶だったが、なんとか全快させることができた。 毎日が奇跡:第10章 (集英社文庫、大熊栄訳) 11 朝食の時、郵便物と一緒にココアの缶がシーグフリードの席に届く。中身は山羊の糞。美人で金持ちのグラントリーさんは独身で、好意を寄せる人にそれを送り、大切な山羊の精密検査を依頼するのだった。ヘリオットが親切にしてやったときには、彼宛にココアの缶が届いた。ある日、彼女の山羊が怪我をしたので、トリスタンとともに往診する。トリスタンは博学な山羊の知識を披露し、グラントリーさんをとりこにしてしまい、ヘリオットは落ち込む。しかしトリスは前日、山羊が試験に出ると聞いて猛勉強したばかりだった。1週間後、トリスの朝食の席にも山羊の糞入りココア缶が届いた。 毎日が奇跡:第11章 (集英社文庫、大熊栄訳) 12 船内日記10月31日。真夜中から嵐に巻き込まれ、揺れに揺れて船内は滅茶苦茶になる。睡眠不足で朝食を食べに行くと、船長はヘリオットの食欲が落ちないのを見て驚く。昨晩は風力9の暴風雨で、めったにないひどい揺れかただったが、ヘリオットは船酔いしない体質だった。しかし羊たちはストレスで弱り死にそうになっていた。あわててコルチゾンを注射する。ラウムの献身的な看護で2時間後には回復した。ランチはいつもどおり素晴らしかった。夜、船からヘレンに電話をする。 毎日が奇跡:第12章 (集英社文庫、大熊栄訳) 13 床屋のジョシュ・アンダーソンは、ビールが大好きでいつもパブで一杯のビールと引き換えに散髪をしてやっていた。10杯を越えるとひどいヘアスタイルになってしまう。あるとき、彼の犬、ビーナスの歯に鶏の骨がはさまってしまい、来院。ジョシュは手術が怖くてビーナスを押さえられない。麻酔をかけることにし、彼を追い払う。手術は成功したが、ビーナスは呼吸をしていない。あわててビーナスをぶんぶん振り回して何とか蘇生させた。ジョシュが戻ってきたが、ビーナスが死にそうになったことは言わなかった。しかしジョシュはビーナスを触って「空を飛んでいたのか」と言う。ある日、散髪に行って庭のことを考えていると、突然ジョシュが「私もガーデニングは好きです」という。彼は毛を触ると心が読めると言う。驚いたヘリオットは、散髪中はビーナスの手術のことはつとめて考えないようにした。 毎日が奇跡:第13章 (集英社文庫、大熊栄訳) 14 船内日記11月1日。苦労の末、リトアニアのクライペダに到着。水先案内人はとても頼りなく、船長が自ら航路策定をせざるを得なかった。税関関係の人々が乗船してくるが、彼らの衣服はとても粗末だった。しかし、みな快活でよい人たちだった。獣医は太った女性で英語がしゃべれない。古臭い2分計の体温計を使って羊たちを検査したので、検疫に5時間もかかった。日が暮れて、ヘリオットは船長とともにクライペダの町へ。暗がりで恐ろしい犬たちにに襲われそうになる。インタークラブという映画館やダンスホール、図書館が一体になった娯楽施設を訪れる。忙しい一日だった。 毎日が奇跡:第14章 (集英社文庫、大熊栄訳) 15 捨犬の世話をボランティアでやっているローズ看護婦長の依頼で、アンバーという捨犬を診察する。彼女は美しく人懐っこい犬だったが、皮膚病を患っていた。古臭い軟膏を処方するが、アンバーの皮膚病は治らない。顕微鏡でその皮膚を見てみると、たちの悪いデモデクティックというダニが原因の疥癬で、治療は非常に困難だった。ヘリオットはアンバーを家に連れ帰り、庭の馬小屋の囲いの中に入れて、夜の往診から戻ってくるたびに、治療を続ける。容態はさらに悪くなり、望みはなかった。安楽死させざるを得なかった。今でも、暗闇の中の、車のヘッドライトビームに照らされたアンバーの姿が頭から離れない。 毎日が奇跡:第15章 (集英社文庫、大熊栄訳) 16 1947年の冬は大雪だった。雪に閉じ込められたデイルに住むバート・キーリーから電話。豚のポリーが子豚を出産したが、お乳が出ず、仔豚たちが飢え死にしそうだとのこと。この仔豚たちはバートの娘、テスの大のお気に入りで、もし何かあったら彼女はどんなに悲しむか分からない。ピチュイトリンの注射が必要だった。ヘリオットはスキーでバートの農場に出かけたが、ブリザードに巻き込まれて遭難しそうになり、たどり着けなかった。そのとき、牛の後産を処理していたときに、子宮頚部を刺激すると条件反射でミルクを出したことを思い出す。早速バートにそのやり方を電話で教える。大成功、テスは悲しまずにすんだ。 毎日が奇跡:第16章 (集英社文庫、大熊栄訳) 17 ブロートンでヘレンと映画を見に行ったとき、彼女が産気づいた。慌ててダロウビーに帰る。翌朝6時に、いよいよ産院へヘレンを連れて行く。スケルデールハウスに戻って悶々として待っていると、11時にアリンソン先生から「ジミーに妹ができた!」と電話。大急ぎで産院へ。ジミーのときと同じへまをしてしまい、ブラウン助産婦に追い出される。知り合いに電話を入れまくる。黒牛亭で誕生祝賀会。いちいち飲物を買いに行くのが面倒になり、パブの亭主に財布ごと預け、飲みまくる。閉店時間法に違反し、ドアに鍵をかけ、店の照明を落として地下室でドンちゃん騒ぎをやっているとと、超堅物のお巡りさん、グール氏がやってきた。険悪な雰囲気になりかけたが、トリスタンがグール氏の犬、ジュリーはヘリオットが診なかったら死んでいたことを思い出させ、結局グール氏も宴会に参加してしまう。グール氏は飲み始めると、人が変わってしまい、日ごろの謹厳実直さはどこへやら。パブからの帰り道、グール氏がいつも目の敵にしている同僚が夜の歩哨に立っているのを見つけ、罵声を吐き掛けそうになり、大いに慌てる。スケルデールハウスに戻り、ロージーを得てより豊かになったことを実感する。 毎日が奇跡:第17章 (集英社文庫、大熊栄訳) 18 船内日記11月2日。夕方まで羊たちを下ろすことができないので、船長とクライペダの町を探検に行く。市中の店はどれも薄汚く魅力がなかった。女性たちが肉体労働をしているのを見て驚く。学校に行ってみる。許可証を持たずに職員室に行くと、警備兵を呼ばれてしまう。しかし、英国とソ連の教育システムの違いなどについての質疑応答でなごやかな雰囲気になると、兵たちは出て行った。船に帰るとソ連人の獣医が待っており、咳をしているリンカーン種の羊について尋ねられた。コックのニールセンはタルタルステーキのサンドイッチを作ってくれたが、生肉は初めてでびびってしまうも、食べてみると美味かった。夜の8時にようやく羊たちをおろすことができた。いよいよ出港しようというときには、再び嵐が近づいてきていた。 毎日が奇跡:第18章 (集英社文庫、大熊栄訳) 19 ビギンズ氏は、その頑固さと吝嗇さで、頭痛の種だった。戦争が終わり、より年をとった彼はいよいよ頑固で偏屈になっていた。彼から牛がおかしいとの電話をもらったが、死にかけているので来なくてもいいかも、みたいなあいまいな頼み方。10分後に往診すると、「来るのが遅すぎるから、もう死にかけている」とヘリオットのせいでにする。注射を打ってやるが、手遅れですぐに死んでしまう。「注射で殺したんでねーべか」とビギンズが疑うので、採血して顕微鏡で確認してみるが、何も見つからず、かえって検査代の無駄になっただけ。ある日、彼が「牛が木の舌病になったのでヨードをくれ」と来院。シーグフリードは「ヨードなどは時代遅れで処方できない」と断り、無理やりサルファ剤を押し付ける。数日後、ビギンズの農場に立ち寄ってみると、サルファ剤が使われないまま放置されていた。ビギンズはヨードを薬局で買って牛の舌病を治そうとしたのだが、かえってひどくなっていた。懲らしめのため、シーグフリードは「これは特効薬だ、しかしサルファ剤を飲ませないと、死に至る劇薬だ」と単なるビタミン剤を注射するのだった。ビギンズはサルファ剤を使わざるを得なかった。 毎日が奇跡:第19章 (集英社文庫、大熊栄訳) 20 ハドソン兄弟の農場でツベルクリンテストをやっていると、保険屋のジョージ・フォーサイスがやってきて、しきりに生命保険を売りつけようとする。兄弟は「ハドソン家はみんな長生きだし、病気にもかからん。そもそも保険は信用できん。」と相手にしない。ジョージは「農場の仕事は危険だから、傷害保険はいかが。年間10ポンドで、怪我の際には週当たり20ポンドもらえますぜ。若いハーバートは5ポンドでいいです。」と勧め、何とかサインさせるてしまう。ある日、ダロウビーで、洒落たスーツを着た兄のクレム・ハドソンに会う。腕を骨折し、全治10週間以上。200ポンドせしめたのだった。また、農場に行ってみると弟のディックが松葉杖。足の骨折で全治14週間。若いハーバートは干草用熊手を踏み抜いて敗血症になり全治10週間。25ポンドの元手で、700ポンドももらったのだった。保険会社は来年の契約は更新しないと言って来た。彼ら兄弟は他の傷害保険、自動車保険に入り、その都度しっかりもうかってしまい、いまや保険の熱烈な信者となってしまったのだった。 毎日が奇跡:第20章 (集英社文庫、大熊栄訳) 21 船内日記11月3日。外洋は嵐で荒れまくり、ほとんど眠ることができなかった。行きの嵐は左右に揺さぶられたが、今度の嵐は前後への揺れであり、もっとたちが悪かった。朝になって、コックのニールセンが軽い朝食を持ってきてくれる。彼は揺れる船の中で髭を剃っているヘリオットを見て驚く。食堂に行き、たっぷり朝食をとる。羊たちもいなくなり、することもないので、寝そべって本を読んですごした。ランチの後にもニールセンがスナックとビールを持ってきてくれる。もちろんディナーもいつもどおり豪華、船に乗って以来、太ったのは間違いない。船はポーランドのステッティンに行き、800匹の豚を積んでドイツのリューベックに行くことになる。 毎日が奇跡:第21章 (集英社文庫、大熊栄訳) 22 ジミーが学校に行くようになって、往診の際に一緒に乗って行ってくれる仲間がいなくなり寂しい思いをしていたが、小さなロージーが彼に取って代わった。ロージーは車に乗るといつも、ラディオグラムで覚えた歌を歌ってくれた。私は昔から音楽が大好きだったので、カタログを取り寄せ、試聴を繰り返し、新しいラディオグラム、マーフィーを買ったのだった。ロージーは3歳だったのに、マーフィーのエキスパートになり、自分の好きなレコードを間違えずにかけることができた。お気に入りはビング・クロスビーで、特に「ケアレス・ハンド」が好きだった。ある日農場の往診の際に、ロージーが暴れ牛に殺されそうになったが、かろうじて助かり、安堵する。ロージーは往診の車中で、私とのクイズを楽しみにしていた。彼女が就学するとき、彼女は私の助手がいなくなることを大いに心配してくれ、週末には必ず手伝うと約束してくれた。彼女は獣医になりたがったが、私は彼女に汚れ仕事をさせるのが嫌で、人間の医者にしてしまった。でも、いまだにそれが良かったかどうか悩む。 毎日が奇跡:第22章 (集英社文庫、大熊栄訳) 23 1950年に、英国の高名な劇作家、ジョージ・バーナード・ショーがりんごの木を剪定しているときに骨折する、という事件があった。この事件はマスコミにも広く紹介され、連日新聞の見出しをにぎわせた。あるとき、ムーアの奥地に孤立しているカスリング家の農場での出来事。牛が骨折したと言うので、往診する。カスリング家は全員ひどく無口だった。骨折した牛にギプスをはめているとき、なんの会話もなくて気まずい思いをしたので、「バーナード・ショーみたいですね」と骨折を話題にする。しかし、彼らはショーを知らず、話は途切れてしまう。彼らにとって、その近くに在住する人以外は話題にならなかったのだ。 毎日が奇跡:第23章 (集英社文庫、大熊栄訳) 24 船内日記11月4日。嵐は相変わらずで、この日も一日ベッドで本を読んで過ごす。揺れはひどく、シャワーに出かけるのにも苦労する。シャワーに行く途中に船員の根棚を見ると、何人もの屈強な船員が寝ている。彼らも船酔いしたのだろうか。船内日記11月5日。船はポーランドのステッティンに到着した。出港するまで2時間あるので、市中を見に行く。クライペダに比べてより快適で文明のにおいがしたが、レーニンの大きなポスターを見て、まだ鉄のカーテンの向こうにいることを実感する。船に戻って豚を積み込む。英国の豚に比べてはるかにおとなしい。この日は結婚記念日だったので、コックは英国風の料理を作ってくれた。船内日記11月6日。リューベックに到着し、列車でハンブルグに出てそれから飛行機でヒースローへ。私の旅は終わった。船長にとっては私はやっかいものだったが、コックのニールセンは私がいなくて寂しがっているだろう。 毎日が奇跡:第24章 (集英社文庫、大熊栄訳) 25 日曜日の夕方にギルソープのカンドールさんから電話。往診してみると、ダックスフンドのハーマンの足が麻痺して歩けなくなっていた。原因が分からないので、一般的な処方を施す。飼い主のロン・カンドールは炭鉱事故で寝たきりだった。彼と一緒にビールを飲みながらデイルズの素晴らしさを話し合う。その後、何回か往診するが、ハーマンの麻痺は良くならない。ある往診の際、異様な匂いが漂っていた。ロンの友人、ビル・ノークスがくれたアギと言う得体の知れない薬だった。しかし、ハーマンは数週間後、自然治癒したのだった。ハッピーエンドはいつも楽しい。 犬物語:第9章 (集英社文庫、大熊栄訳)
毎日が奇跡:第25章 (集英社文庫、大熊栄訳)26 戦後、人工授精が一般化して、牡牛を買う余裕のない農夫たちには福音となった。しかし、私の最初の人工授精はうまくいかなかった。ゴムでできた人工膣にお湯を入れて温め、それを使って牡牛の精子を採集する仕掛けなのだが、ハートリーさんの農場で試してみると、牡牛のペニスを人工膣に入れるのがうまくいかず、牡牛を怒らせてしまったのだ。困って農業省に電話を入れると、明朝、専門家を農場に送ると言う。翌朝、農場に行ってみると、その専門家とはトリスタンのことだった!彼に昨日の顛末を話すと大笑いされた。牡牛のペニスをつかむ必要などなく、もっと簡単な方法でよかったのだ。トリスタンの指導の下で再度、人工授精を試みるが、人工膣に入れたお湯が熱すぎて、また牡牛は逆上してしまう。再度試み、ようやく3ccの精子を採集することができたのだった。 毎日が奇跡:第26章 (集英社文庫、大熊栄訳) 27 ジャック・スコットは優しい農夫で、どの動物もまるでペットのように扱った。彼のところの子羊が転んでばかりいるので、診察してみると、銅の欠乏による脳症で、治療法がない。安楽死をほのめかすが、彼はそうせずに「チャンスをあげる」と言って、そのまま飼い続けるのだった。シープドッグのリップの右の前足が麻痺する。さらに右の後ろ足を骨折してしまう。治療にもかかわらず、骨はつかない。しかしジャックは諦めずに飼い続け、やがてリップは2本足で走ることができるようになった。また、牛のブランブルが脳の障害で、まっすぐ歩けなくなり、丸を描くように歩くなってしまう。ヘリオットの治療はまるで効かない。しかしジャックは諦めずに飼い続け、やがて治ってしまう。しかしブランブルは面白いしぐさをするようになった。まるで魅力的な妖婦のように色っぽいまなざしで見つめるのだ。ジャックはブランブルをダロウビーのショーに出した。審査委員長のローワン准将はチャンピオン候補を決定するために最後に残った3匹の審査をする。そのとき、ブランブルのこの色っぽいしぐさを見て、たまらずチャンピオンにしてしまったのだった。 毎日が奇跡:第27章 (集英社文庫、大熊栄訳) 28 変わった畜主たち。若いデリック夫妻は田舎暮らしがしたくて最近ダロウビーの近くに引っ越してきた。デリック氏はトマトを大切に育てており、毎日その数を正確に勘定している。ある日彼らの山羊が293個のトマトを全部食べてしまい、大騒ぎになる。またループとウィルのラウニー兄弟は喧嘩ばかりしており、大して違うことをやっていないのにいちいち相手を批判している。獣医学に精通している農業大学卒のインテリ農夫がいると思えば、昔ながらの曖昧なテッド・バックルみたいな農夫もいる。ボッグ氏はけちで有名な農夫で、医院で「約1000錠あるよ」と渡した錠剤を「987錠しかない」と文句をつける。しかし彼から1ダースの卵を買ったとき、11個しかなかったと文句を言うと、「そのうちの1個は黄身が双子だべ」と言いぬける。また、夏の盛りに短パンで仕事をしにいくと、クラウチングスタートの格好で競争を挑みかかるミーネルさんみたいな農夫もいるのだった。 毎日が奇跡:第28章 (集英社文庫、大熊栄訳) 29 1963年にジョン・クルックスがまたイスタンブールへの旅行の話を持ってきた。彼の話によれば、家畜運搬船の添乗獣医で、17日間の地中海クルーズ、イスタンブールでは5つ星ホテルに泊まる豪華旅行とのこと。早速予約を入れる。8月になって輸出会社から電話がかかり、ガトウィック空港に集合とのこと。今回は飛行機で運搬し、4日間の旅と聞いてちょっとがっかり。8月8にガトウィック空港に行くと、そこで待っていたのは老朽機グローブマスター。40匹のジャージー種の若牛を運ぶのだった。ジャージー島の農夫、ノエルとジョーも一緒だった。午後8時離陸の予定が、結局真夜中になる。ミュンヘンで給油した後、南下。朝起きて驚く。エンジンの一つが火を噴き、止まっていた。しかし、なんとかイスタンブールにたどり着く。 毎日が奇跡:第29章 (集英社文庫、大熊栄訳) 30 9歳のジミーはリビングストンさんにピアノを習っており、発表会にのぞむことになった。他の生徒の演奏の最中に、その親を見ると、みんな緊張していた。そしてジミーの番がやってきた。The Miller's Danceと言う曲を演奏するのだが、曲の途中で止まってしまう。リビングストン先生ははじめからやり直すように言う。しかし、ジミーの演奏は同じ場所で止まってしまうのだった。ヘリオット夫妻は生きた心地がしない。しかしジミーは全然平気。先生は仕方がないので、他の生徒の演奏発表に移る。結局、曲を最後まで演奏できなかったのはジミーだけだった。発表会の最後に、先生はジミーに今一度チャンスを与える。今度はジミーは最後まで弾き通した。万雷の拍手。帰りの車の中で、ジミーは「音楽って大好き、気が休まるもん」というのだった。 毎日が奇跡:第30章 (集英社文庫、大熊栄訳) 31 ウォルト・バーネットは、そのあこぎな商売で町一番の金持ちだった。ある日、彼から往診の依頼。往診してみると、足を怪我した猫、フレッドがいた。ウォルトは金にならない動物を飼うような男ではなかったので驚く。翌週、またウォルトから電話。フレッドがよくならないと言う。往診してよく調べてみると、足にゴム紐を巻かれて、それで皮膚が裂けてしまったのだった。3週間後、またウォルトから往診を頼まれる。今度はフレッドの首にゴム紐が食い込んでいた。ウォルトは、そのあこぎな金儲けで敵がたくさんいたので、嫌がらせとしか思えなかった。1年後、また電話。「フレッドが毒を盛られた」という。往診してみると、毒ではなく猫ジステンパーだった。毎日往診したにもかかわらず、フレッドは死亡。ウォルトは泣いていた。フレッドはこの悪漢の唯一の友達だったのだ。ヘリオットは初めてウォルトに好感をいだいた。 毎日が奇跡:第31章 (集英社文庫、大熊栄訳) 32 1963年8月9日。イスタンブールの空港到着後、牛たちを下ろそうとするが、昇降機が故障してしまい、午後4時になってようやく牛の積み込みが完了する。しかし、事務的なミスで、積み込んだ牛がトルコ側の書類と一致せず、15番の牛を持って帰れと言われてしまう。農夫のジョーの交渉で、なんとか受け取ってもらえた。しかしエンジンの故障のために、グローブマスターに乗って英国に戻ることはできなくなってしまった。さらに悪いことには、トルコの祝日のために、ホテルが予約できない。しょうがないのでボスポラスの街道沿いの小さなホテルへ。5つ星ホテル夢ははかなく潰える。24時間ぶりに食べるトルコ料理は美味かった。郵便局で輸出会社に電話をかけて帰国について相談しようとするが、電話がつながらない。その後、ビールを求めてイスタンブールの町へ。イスラム圏なので甘い飲み物ばかり。流行っているレストランに入って見ると、ここも甘い飲み物ばかり。しかもウェイターは料金を受け取らない。おかしいと思って回りを観察してみると、なんと間違って結婚披露パーティにまぎれこんでしまったのだった。 毎日が奇跡:第32章 (集英社文庫、大熊栄訳) 33 1950年代には、牛の角は除去するのが当たり前になっていた。危ないし、ミルクの産出量には関係ないからだ。しかし、牛の角を除去する仕事は獣医にとってやっかいなものだった。小さな牛の角の除去に垣根の剪定ばさみを使っていたが、大きな牛はギロチン装置を使わざるを得ず、これは血のシャワーが吹き出て大騒ぎになることが多かった。10月のある日、グラスゴー時代の旧友、アンドリュー・ブルースがダロウビーに立ち寄った。彼は銀行員をしていると言う。ヘリオットが往診に行くとき、アンディも一緒についてくると言う。デイルズの素晴らしい風景を見て、アンディは「こんなところで仕事のできる人がうらやましい」と言う。ダニングさんの農場での牛の角の除去は戦慄すべきものだった。ヘリオットも農夫たちも、巨大な牛の角の除去にはひどい目にあった。それを見てアンディは「僕の今の仕事にも良いところがあるよね」と言うのだった。 毎日が奇跡:第33章 (集英社文庫、大熊栄訳) 34 またコンデンスミルクの缶に鼻面をつっこんでしまったブランディを連れて、ウェストビー夫人が医院にやってきた。ブランディは愉快な雑種犬で、他の犬がしないようなことをするユニークな性格だった。ごみ箱あさりもその一つで、しょっちゅういろんな空き缶に顔を突っ込んで取れなくなり、医院に連れてこられるのだった。水泳が原因でブランディが肺炎になってしまう。抗生物質のおかげで、何とか命拾いはしたものの、往年の元気はよみがえらなかった。あるとき医院に二本足で立って歩くプードルがやってくる。それを見て私はブランディのユニークな振る舞いを思い出した。そのときなんらる偶然か、ブランディが連れてこられた。鼻面をトマトスープ缶に入れて。ブランディの肺炎はようやく自然治癒し、また元通りの愉快な振る舞いをする犬に戻ったたのだった。 犬物語:第10章 (集英社文庫、大熊栄訳)
毎日が奇跡:第34章 (集英社文庫、大熊栄訳)35 1963年8月10日。結局イスタンブールを観光することはできなかった。朝食後、空港に行ってヒースロー行きの航空券を買おうとするが、個人用小切手は受け付けてもらえない。しょうがないのでヘリオットと農夫たちは、再びグローブマスターに乗って帰国したいと機長に相談する。機長は命の保障はしないし、そのことを記した念書にサインしなければ乗せる事ができないと言う。命の危険を知った上で、彼らはグローブマスターでコペンハーゲンに向かい、なんとか無事着陸。夜中の2時にヒースローに向けて出発し、早朝にキングスクロスの駅に到着。ヨーク駅に着くまで眠りこける。数ヵ月後、そのときのグローブマスターが乗員ごと地中海に墜落したとのニュースを聞いた。それが嘘であることを今でも祈っている。 毎日が奇跡:第35章 (集英社文庫、大熊栄訳) 36 ウィットホーンさんのところのウェスト・ハイランド・ホワイト・テリア、ラッフルズとマッフルズはわがままで危険な犬たちだった。往診するたびに手荒く迎えられ、噛み付かれるのだが、飼い主は犬たちを甘やかし、きびしく怒ることができないのだった。その家にミルクを配達しているダグ・ワトソンによれば、これらのウェスティーズも、昔はとてもかわいい子犬だったとのこと。またシーグフリードによれば、飼い主が甘やかしすぎたから、そんな凶暴な性格になってしまったとのことだった。ところがラッフルズとマッフルズが相次いで死んでしまう。ウィットホーンさんはまたウェスティーズを2匹飼うことになった。名前は先代同様ラッフルズとマッフルズ。とても性格の良い子犬だった。1年後訪問してみると、先代のウェスティーズたちと同じように性質の荒い犬になっていた。また甘やかしてしまったらしい。診察の最中、ラッフルズがウィットホーン氏の親指に噛み付く。あまりの痛みに飼い主はラッフルズをどなりまくる。私はようやくしつけができる、と思ったのだった。 毎日が奇跡:第36章 (集英社文庫、大熊栄訳) 37 道路工事夫のライオネル・ブラフは、様々な動物を飼っていた。彼の動物小屋はベニヤ板やなまこ板、金網など雑多なもので仕切られており、それぞれの動物のところにたどりつくまでひどく苦労する構造になっていた。ある日、ライオネルは豚を大規模に飼ってみたいと言い出した。伯父が死んで遺産が入ったので長年の夢を実現したいとのことだった。あっという間に立派な豚舎が建設された。しかし、豚の世話は大変で、かつてののんきなライオネルは忙しく働かざるを得なかった。ある日、ライオネルから電話。豚たちの調子が悪いと言う。往診してみると、豚コレラの疑い。農業省がなかなか認定してくれなかったが、それが幸いして健全な豚たちを食肉業者に売りさばくことができた。しかし豚は全滅。ライオネルは諦めなかった。4ヵ月後、また豚舎は一杯に満たされた。すると、また異常が起きた。突然豚たちが痙攣を始めたのだ。ヘリオットはまた豚コレラかと思って憂鬱になるが、調べてみると、水を長時間飲まなかったことで起きる「塩害病」だった。水を飲ませて事なきを得る。しかしライオネルは豚の大規模経営にはこりごりして、またもとの雑多な動物小屋へ戻っていくのだった。 毎日が奇跡:第37章 (集英社文庫、大熊栄訳) 38 ある6月の日曜の朝、マット・クラークさんの農場のキッチンで手を洗わせてもらっているとき、クラークばあさんが編み物をしているのを見つける。彼女は80代後半の女性で、農場でも家庭でも苦労し続けてきた人だった。ばあさんにロージーを紹介する。ばあさんはヘリオットに、「今は分からんかもしれんが、実はおまえさんは、人生の一番良い時代を過ごしてるんだよ」と言われる。スケルデールハウスに戻ると、シーグフリードが彼の子供、アランとジャネットに車のトランクの整理を手伝わせているところだった。シーグフリードと裏庭に出て寝そべり、昔話にふける。彼にクラークばあさんとの会話を伝えると、シーグフリードもばあさんの意見に同意した。成長しつつある子供たちと毎日一緒に往診に出かけられることほど幸せなことはない、と彼も言う。さらに彼は「獣医としても一番良い時代を過ごしている」とも言う。新薬や新治療法の出現で、数年前までは夢のようだった治療ができるようになったからだ。そして、「我々にはさらに素晴らしい将来が待っている」、と彼は言うのだった。 毎日が奇跡:第38章 (集英社文庫、大熊栄訳)